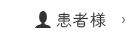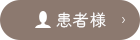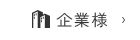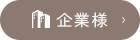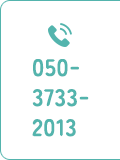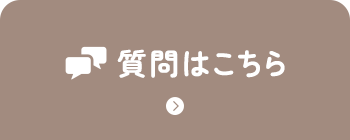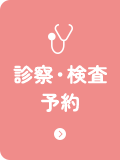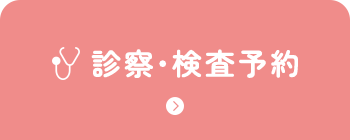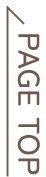目次
肝臓の異常は、自覚症状が現れた頃には病気がかなり進行しているといわれるため、早く気付くには健康診断などの検査が有効です。
しかし、健康診断の結果がよくない場合に耳にする『肝臓の数値が高い』とは、一体どういうことなのでしょうか?
この記事では、肝臓の数値とはどのような数値のことか、数値が高い場合に疑われる病気、改善する対処法などを紹介します。
健康診断で肝臓の不調を知ったときの参考にしてください。
肝酵素とは
肝臓は酵素を使いこなし、複雑かつさまざまな化学変化を起こして消化吸収を担うため、臓器のなかでも高性能といわれています。
肝臓の具体的な働きは以下の通りです。
脂肪を消化するための胆汁を分泌する 食べ物を身体が吸収できるよう変化させ、蓄える 体内に入った有害物質を分解・解毒する 強く大きな働き者であり、異常が起きても症状として現れづらい肝臓ですが、健康診断では数値としてその不調が明るみになります。
ここでは肝酵素について、基準値も含めて紹介します。
逸脱酵素
肝臓は、血液検査によってどの酵素がどの程度血液中に漏れ出ているかを知ることで、異常が分かります。
酵素をもつ臓器(肝臓や心筋・骨格筋など)の細胞がなんらかの原因で障害されると、組織が破壊され血液中に酵素が漏れ出ます。
この酵素を逸脱酵素といいます。 肝機能の検査では、血液に逸脱酵素がどのくらい漏れだしているかが数値で分かります。
一般的に健康診断で『肝臓の数値が高い』と言われているのは『逸脱酵素が規定値以上の数値で漏れ出しているため異常がある』ことを示しています。
肝酵素が高いことと肝機能に低下があることはイコールではないので注意してください。
AST(GOT)
ASTはアスパラギン酸アミノトランスフェラーゼと呼ばれる、肝臓に多く含まれている酵素で、肝細胞が破壊されることで血液中に大量に放出され、数値があがります。
アミノ酸を作る働きをもちますが、肝細胞以外に心筋や骨格筋にも含まれているため、後述するALT(GPT)の数値も確認したうえで、なんの病気かが推測されます。 ASTの基準値は30U/L以下で、これより低い場合でも問題はありません。
ALT(GPT)
ALTは肝細胞に最も多く含まれている酵素で、アラニンアミノトランスフェラーゼと呼ばれます。
ALTの数値が高い場合は、肝臓に異常があると考えられます。
AST同様、アミノ酸を作る酵素で基準値は30U/L以下、AST同様これより低い数値でも問題ありません。
γ-GTP(γGT)
γ-GTPは肝臓の解毒作用に関連する酵素で、ガンマグルタミルトランスペプチダーゼと呼ばれます。
肝臓病や胆道系の病気にかかっていると数値が上昇します。
また他の逸脱酵素と違い、解毒などの必要があり分泌されるため、病気がなくても上昇することが有ります。
基準値は男性79U/L以下、女性は48U/L以下で、過度の飲酒が原因でγ-GTPだけ数値が高くなることがあります。
そしてγ-GTPは低すぎても不調の原因となります。
ALP
ALPは、肝臓(胆管)や、骨・腸・腎臓など多くの臓器に含まれているアルカリ・フォスターゼと呼ばれる酵素です。
これらの臓器が障害を受けることで血液中に漏れ出て数値があがりますが、ALPは胆汁にも排出されます。
検査の数時間前の食事内容が脂肪の多いものの場合にも検査値が高くなります。
基準値は検査を受けた医療機関によって異なります。
日本人間ドッグ学会では80~260U/L 国際臨床化学連合(IFCC法)では38~113U/L 日本臨床化学会(JSCC法)では106~322U/Lから38〜113U/L ALPの値は、低すぎる場合も疾患になる場合があります。
LDH(LD)
LDH(乳酸脱水素酵素)は逸脱酵素では一番有名なもので、肝臓・赤血球・筋肉・悪性腫瘍などにある酵素です。
正常値は200~400U/Lほどですが、悪性腫瘍の場合は数千まで上がることもあります。
LDHに関しては5種類(LDH1~LDH5)まであり、病気によって数値が上がる種類が変わるため、たんぱく質の構造が異なる酵素(アイソザイム)を検査で分類して種類を測定します。
アイソザイムは産生される臓器によって組成が異なるため、どの臓器に異常があるのかが特定できるとされています。
他の肝酵素と共に上昇している場合は肝臓疾患の関連を考えます。
総ビリルビン(T-BIL)
総ビリルビンは血液検査で測定できる黄色い色素の値で、肝臓や胆のう・胆道に異常がある場合に血液中に増え、黄疸を引き起こします。
老化した赤血球が分解される際に生じる色素で、通常は処理されたあとに胆汁に排泄されます。
しかし、肝臓に障害が起こることで胆管へ運ぶ働きが低下してしまうため、血液中に漏れ出し数値が上昇します。
ビリルビンには直接ビリルビンと間接ビリルビンがあり、両方を合わせて総ビリルビンとなります。
どちらかの数値が高い場合や、総ビリルビン値が基準値の0.2~1.2mg/dLに比べて値が高い場合に、疾患の恐れがあります。
その一方で体質的に高い方が存在し、体質性黄疸と言われます。
数値が高いと疑われる疾患
血液検査で判明した各酵素の数値が高い場合、数値によって疑われる疾患が分かります。
以下で紹介するように、基準範囲を大きく超えるような場合、入院して肝生検による詳細な検査や治療が必要となる場合があります。
肝生検は腹部から針を刺して肝臓の組織を採取しますが、麻酔を施すため通常は1~2日の入院が必要となります。
基準値については各医療機関において若干の差はありますが、一般的に考えられている可能性として紹介します。
ASTとALTが高い場合
ASTとALTはどちらも基準値が30U/L以下で、肝臓に障害がある場合に血液中の数値が上がります。
ASTは肝細胞以外にも心筋や骨格筋にも含まれるため、肝臓のみに含まれるALTの数値と照らしあわせて状態を判断することから同時に測定します。
疑われるケースと疾患は以下の通りです。
ASTがALTより高い:肝硬変、アルコール性肝炎など
ALTがASTより高い:急性・慢性肝炎、脂肪肝など
ASTだけが高い:心筋梗塞、多発性禁煙、溶結性貧血など
AST・ALTのどちらも500U/L以上の場合は急性肝炎の疑い
γ-GTPが高い場合
γ-GTPは肝臓の解毒作用に関係がある酵素で、この値によって胆管や胆のうの疾患も推測できます。
飲酒に対する反応が敏感な酵素で、過度な飲酒により数値が上昇しやすいですが、健康な人はすぐに数値が下がるため区別はつきます。
γ-GTPの値が高い場合に疑われる疾患は以下です。
アルコール性肝障害 閉塞性黄疸 胆石症 肝炎 急性膵炎など γ-GTPの値が500U/Lの場合は、アルコール性肝機能障害などの疑いがあります。
ALPが高い場合
ALPの数値が高い場合に疑われる病気は以下の通りです。
閉塞性黄疸、薬物性肝障害、胆管炎、甲状腺機能亢進症、骨腫瘍など肝臓以外の疾患の際も数値に現れます。
特に400U/L以上になると胆道がん、胆石、胆がんなどの疑いがあります。
ALPは胆道の疾患で数値が上がりますが、肝臓の疾患ではあまり上がらないため、他の酵素の数値と併せて判断する際に役立ちます。
またALPは逆に値が低い場合、骨や歯が弱くなり骨折や歯がぬける症状が見られる低ホスファターゼ症や亜鉛・マグネシウム不足、ステロイド薬の使用などが原因での問題を引き起こしている場合があるため、注意が必要です。
LDHが高い場合
LDHは細胞内で糖がエネルギー変換される際に働く、肝疾患以外にも数値が上昇する酵素です。
LDHの値が高い場合でも他の肝酵素に異常がない場合は肝疾患以外の疾患を考えます。
総ビリルビンが高い場合
肝臓の調子が悪いときに現れる有名な症状の黄疸は、ビリルビンの数値が高くなって現れる症状です。
総ビリルビンの値が高い場合に疑われる疾患は以下の通りです。
急性・慢性肝炎、肝硬変、肝がん、胆石・総胆管結石など胆管の閉塞、溶血性貧血、体質性黄疸
総ビリルビンが高い場合、腹部超音波検査やMRI検査が行われます。
治療としては、アルコールと食べ過ぎを控えて生活習慣の改善が行われます。
肝臓の数値が高かったら
肝臓に関しては、症状が何もなければ健康診断を、気になるところがあれば受診して、肝臓が今どのような状態なのかを把握してみるといいでしょう。 肝臓は調子が悪くても自覚症状として現れないため放置されがちですが、疾患が見つかったときには治療が困難な状態まで進んでしまっている場合もあります。 しかし早期に発見できれば、今は肝硬変でも治る可能性がある時代です。
健康な肝臓と長く付き合っていくためのメンテナンスとして、定期的な検査をおすすめします。
まとめ
『沈黙の臓器』といわれる肝臓は自分からその症状をなかなか訴えてきませんが、血液検査をするとさまざまな情報から事細かな状態がきちんと分かります。
長く健康に働いてもらうためにも『肝臓の数値』を一度調べてみましょう。
では、血液検査のほかにも腹部エコー検査やフィブロスキャン検査など、肝臓を総合的に診ていきます。
肝臓の数値に異常があった場合でも、一人ひとりの患者さんの状態をそれぞれ総合的に判断したうえで結果を診ていきます。 安心しての肝臓内科医にご相談ください。
腹部の超音波検査(エコー検査)~脂肪肝、肝機能異常、胆石、胆嚢ポリープ、膵臓チェックも~
肝臓の採血検査~肝機能、肝臓繊維化、肝炎など~
著者
東長崎駅前内科クリニック 院長 吉良文孝
日本消化器病学会認定 消化器病専門医
日本消化器内視鏡学会認定 内視鏡専門医
日本肝臓学会認定 肝臓専門医
日本消化管学会認定 胃腸科指導医
日本糖尿病学会
日本肥満学会
平成15年 東京警察病院
平成23年 JCHO東京新宿メディカルセンター
平成29年 株式会社サイキンソーCMEO
平成30年 東長崎駅前内科クリニック開院