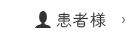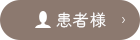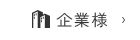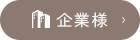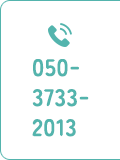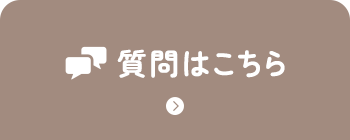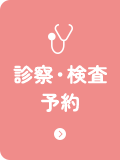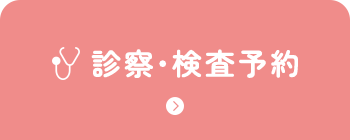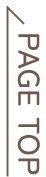目次
月・水・土 午前藤岡医師 または 金曜日 吉良医師 の外来をご受診ください。
不定期で別医師が診療にあたることもありますので、医師診察予定を予約サイトなどでご確認のうえ、受診予約をして下さい。
消化器漢方(お腹の東洋医学)
和光市・志木市・朝霞市の地域にお住まいの皆様へ。
「さいたま胃腸内視鏡と肝臓のクリニック和光市駅前院」では、西洋医学に止まらず、漢方も考慮した東洋医学による治療も積極的に実施をしております。
特に消化器系の疾患やお腹の症状については、他の内科疾患と比較して漢方治療との相性が非常に良いケースが多いのが特徴です。
漢方薬については、効果が現れるまでに時間がかかるというイメージがあるかもしれません。
しかし、その中には、即効性をある程度期待できるものも存在します。
西洋医学においては、「この薬を服用すれば治ります」「降圧剤を用いれば血圧が下がります」といった、病名に直接対応した明確でわかりやすい処方箋が多いです。そしてその薬の効果は非常に確実です。
それに対して、東洋医学、特に漢方を用いた治療では、単に病名に焦点を当てるのではなく、患者ご自身の症状や状態に応じて、その都度処方の内容を変更するという考え方があります。
西洋医学における同一の病名であっても、漢方による処方内容は異なる可能性があります。つまり、一種のオーダーメイド治療に近い形と言えます。
私たちの院では、東洋医学だけ、あるいは西洋医学だけという偏ったアプローチは採らず、両者のメリットを最大限に活用した治療法を提供しています。西洋と東洋が互いに補完し合う形で使用することが重要だと考えています。
即効性、確実性の西洋医学・遅効性、幅の広い漢方の両方を使用して治療を行います。
また漢方を専門にしている場合は、漢方使用を優先することによって、検査がおろそかになってしまうケースがあるのも事実です。
そのような事態を避けるために、当院では検査自体を徹底的に行い、患者さんの健康状態を正確に把握することに力を入れています。
漢方を本当に使うのが適切なのかを判断します。
漢方を使用することが目的になるのではなく、あくまで患者さんの健康状態改善が目的であり、そのための一つのツールが漢方であるという視点を持つことが重要です。
それぞれの治療法には利点と欠点がありますが、その両方を理解し、患者さん一人一人の病状と体質に合った最適な治療を提供することを目指しています。
和光市・志木市・朝霞市にお住まいの皆さんにとって、当院が安心して治療を受けられる場所であることを願っております。
漢方治療に興味がある方、または既に西洋医学の治療を受けているが満足できていない方など、お気軽にご相談ください。
私たちは、皆さんの健康と快適な生活のために、全力を尽くします。

漢方薬の特徴は以下の通りです。
- 複数の生薬の組み合わな複数の症状にまとめて対応できる。
西洋医学の場合は、複数の薬剤が処方されることが有ります。 - 味やにおいにも治療効果がある。
西洋医学ではない考えです。 - 診断名が同じ場合でも処方薬は患者さん毎に変えることがある。
西洋医学では基本的に病名と薬は1対1対応です。 - 診察時の状態や時期によって同じ症状であって漢方を変えながら治療をしていくことがある。
西洋医学は同じ薬を継続するケールが多い。 - 合う薬を時間をかけて探していくために、長い付き合いが必要。
西洋医学では、病名の時点で処方薬がある程度決まります
漢方治療が可能なお腹の病気や症状
便秘
漢方治療の威力が最も発揮しやすいの症状の一つが便秘です。
便の硬さや、お腹の動きの強弱や、ガスの有無など、腹痛がどこにどの様にあるかなどを診察しながら処方を考えます。
また年齢や体質的に虚弱なのかどうかなども参考にします。
近年では便秘の西洋薬も増えてきています。漢方と併用することで治療の効果がより出やすくなります。
便秘の患者さんの中には処方のみを続けている方が多数いらっしゃいます。漫然と処方を受けている場合はは、大腸がんなどのお腹の病気がないかどうかを考える必要があります。
そのため当院では、大腸カメラなどの腸の検査ができるため、本当に漢方治療で良いかどうかの判断を実施して上で対応します。
- 乙字湯
- 麻子仁丸
- 桂枝加芍大黄湯
- 大黄牡丹皮湯
- 大承気湯
- 潤腸湯
- 大建中湯
- 桃核承気湯
- 防風通聖散
- 大黄甘草湯 など
下痢
便秘同様、慢性的な下痢も漢方治療をよく行います。
下痢の場合は急性の下痢(腸炎)など含まれるため、そこを見極めたうえで野治療になります。
また便秘の時度同様に、器質的疾患の除外をしっかりと行います。潰瘍性大腸炎、クローン病などの難治性疾患や甲状腺疾患などがその例です。そのような疾患を除外するために、慢性下痢の方に大腸カメラなどの検査をお勧めしています。
- 半夏瀉心湯
- 五苓散
- 真武湯
- 補中益気湯
- 芍薬甘草湯 など
- 十全大補湯
- 大建中湯
- 桂枝加芍薬湯
- 加味帰脾湯
腹痛・お腹がはる
この症状も非常によく見かける症状です。腹満感・腹痛も漢方で良く対応するものにになります。
便秘下痢同様に、器質的疾患を胃カメラ、大腸カメラ、腹部超音波などの検査で除外したのちに治療を開始します。
痛みタイミング、痛む場所、ガスの有無などでも処方内容や量を調整します。
- 真武湯
- 補中益気湯
- 芍薬甘草湯 など
- 大建中湯
- 桂枝加芍薬湯
胃が痛い・吐気・食欲低下、お腹がすかない、すぐにお腹いっぱいになる
胃に関連する症状は、便秘に次ぐ、漢方との相性が非常に良い症状です。
当院では、漢方治療を進める前に、まず胃カメラによる検査を行い、胃潰瘍やヘリコバクター・ピロリ(ピロリ菌)の感染など、明らかな病変が存在しないことを確認します。
特に、胃潰瘍など器質的疾患が確認されない「機能性胃腸症」と呼ばれる疾患群において、漢方治療は大いに効果を発揮します。これらの症状は機能的な問題から来るもので、それを緩和するのに漢方は非常に役立ちます。
このような胃に関する症状に対する治療においても、西洋医学による薬剤と漢方を併用するケースが多く見られます。これにより、各々の長所を活かした効果的な治療を行うことが可能になるのです。
- 安中散
- 柴胡桂枝湯
- 半夏瀉心湯
- 五苓散
- 抑肝散加陳皮半夏
- 人参養栄湯
- 茯苓飲合半夏厚朴湯
- 人参湯
- 半夏白朮天麻湯
- 補中益気湯
- 六君子湯
- 十全大補湯
- 抑肝散
- 胃苓湯
- 帰脾湯
- 四物湯
- 茯苓飲
- 調胃承気湯
- 平胃散
- 清暑益気湯 など
飲み込みにくさ、喉のつまり感、胸やけ感、呑酸
逆流性食道炎の症状を持つ患者さんの中には、胃カメラによる検査で明確な異常が認められない方がいらっしゃいます。
そのようなケースに対しては、「非びらん性胃食道逆流症」という診断を下すことがあります。
そして、この疾患に対する治療として、漢方を用いるアプローチをとることがしばしばあります。
非びらん性胃食道逆流症は、漢方治療との相性が非常に良いとされる症状の一つです。
つまり、漢方治療によって患者さんの症状改善を期待することができます。
しかしながら、食道がん、好酸球性食道炎などの重大な疾患が隠れている可能性も否定できません。
そのため、当院では、非びらん性胃食道逆流症の診断を受けた患者さんに対しても、定期的な胃カメラによる検査を強く推奨しています。
これにより、早期に隠れた疾患を発見し、適切な治療を行うことが可能になります。
- 柴胡桂枝湯
- 半夏瀉心湯
- 五苓散
- 小半夏加茯苓飲
- 抑肝散加陳皮半夏
- 茯苓飲合半夏厚朴湯
- 補中益気湯 など
- 六君子湯
- 十全大補湯
- 抑肝散
- 胃苓湯
- 平胃散
- 清暑益気湯
消化器領域でよく使われる漢方薬
- 乙字湯
- 安中散
- 柴胡桂枝湯
- 半夏瀉心湯
- 五苓散
- 小半夏加茯苓飲
- 抑肝散加陳皮半夏
- 小建中湯
- 人参養栄湯
- 麻子仁丸
- 茯苓飲合半夏厚朴湯
- 桂枝加芍大黄湯
- 真武湯
- 人参湯
- 大黄牡丹皮湯
- 半夏白朮天麻湯
- 補中益気湯
- 六君子湯
- 十全大補湯
- 潤腸湯
- 抑肝散
- 大建中湯
- 胃苓湯
- 桂枝加芍薬湯
- 桃核承気湯
- 防風通聖散
- 加味帰脾湯
- 芍薬甘草湯
- 四物湯
- 茯苓飲
- 調胃承気湯
- 平胃散
- 大黄甘草湯
- 清暑益気湯 など
よくある質問
副作用のなく体に優しい漢方で治療したいです。西洋薬は副作用があるのでできれば避けたいのですが可能でしょうか?
漢方薬も薬ですから副作用は存在します。完全に安全とは言えません。漢方薬は副作用が全くなく安心安全に服用できると思われがちですが、間違いです。 小柴胡湯という薬の間質性肺炎は最も有名な副作用でしょう。間質性肺炎は、適切な治療を施さない場合、生命を脅かす可能性がある非常に重篤な疾患となります。その他にも、山梔子という生薬を使用した際には、腸間膜静脈硬化症という病状を発症することがあります。これは、静脈が硬化し、血流が悪くなる病気であり、適切な管理が必要となります。
また、自己免疫性肝炎様の肝機能障害を引き起こすものや、皮膚に湿疹を発生させるような効果を持つものもあります。これは、漢方が持つ効果の一部であり、注意深く取り扱うことが求められます。 さらに、一般的な副作用とは少し異なりますが、漢方薬の処方量や患者さんの体調を正しく評価しないと、血圧の上昇や動悸、嘔気などの症状を引き起こす可能性もあります。これらは、適切な量とタイミングでの服用が重要となるためです。 漢方には西洋医学の薬物では得られないような効果がありますが、それが全ての患者さんにとって安全であるとは限りません。医師の指導に従うことが強く推奨されます。西洋薬を何種類も内服することがあるのですが、漢方もいくらでも飲めるのでしょうか?
漢方を3種類以上内服するのは危険と考えたほうがいいでしょうです。
漢方薬は、西洋薬とは異なり、多数の成分(生薬)が一つの製剤に混ざっているのが特徴となります。その成分の一つに、カンゾウという生薬があります。カンゾウは、多くの漢方薬に含まれている成分ですが、その量が過剰になると、体内のバランスを崩し、偽性アルドステロン症という状態になる可能性があります。 偽性アルドステロン症は、血液中のカリウムレベルが低下し、筋肉のけいれんやその他の症状を引き起こす病状です。カンゾウの含有量は、使用される漢方薬によって異なりますが、一般的には、3種類目の漢方薬から注意が必要となる場合が多いです。 特に高齢の方の場合、カンゾウの含有量が少ない場合でも、偽性アルドステロン症を引き起こす可能性があります。実際に、一種類の漢方薬のみで偽性アルドステロン症が発症した事例も報告されています。 したがって、漢方を内服されている方は、その事実を医師に必ず申告することが重要です。種類が多くてもカンゾウの含まれない漢方薬に変える、各漢方の量を減らず、西洋薬に一部切り替えるなどにより、安全に漢方治療を進めることがあります。市販の漢方薬(OTC)が最近沢山あるのですが、処方薬と同じ名前であれば効果は同じですか?
必ずしもすべてが同じではありません。一部の生薬の種類や量が変わっていることがあります。処方される薬とその中に含まれる生薬の構成が大きく変わらない場合もしばしばありますが、同じ漢方名でもメーカーによって考え方が違うため少し違いが出ます。
どの生薬がどの程度含まれているのか、という具体的な構成情報を確認することが重要となります。これにより、漢方薬の安全性と効果を正確に理解し、より適切な治療を受けることが可能になります。西洋薬はあまりのみたくないので全部漢方で治療したいのですが・・・
全てを漢方で解決することが不可能な場合があります。
消化器系の疾患については、漢方だけを用いて治療を進めることが可能なケースが確かに存在します。 しかし、それはすべての病状に当てはまるわけではありません。例えば、糖尿病や高血圧といった病状に対しては、漢方だけでの治療が難しい、あるいは不可能な場合がほとんどとなります。これらの病状は、通常、西洋医学のアプローチを必要とします。 そのため、西洋医学と東洋医学、それぞれの特性と得意領域、限界をきちんと理解し、それらを適切に使い分けることが大切です。 また、その二つが互いに補完しあう形で治療を進めることで、最良の治療効果を得ることが可能となります。 つまり、最終的な目標は、各患者さんにとって最適な治療プランを作り出すことです。そのためには、西洋医学と東洋医学の両方から得られる知識と技術を活用し、それぞれの長所を引き立て、短所を補うようなアプローチが必要となります。漢方は粉なので飲めません・・・どうしたらよいでしょうか?
粒の漢方薬が存在します。。
全ての漢方に粒があるわけではないですが、一部は粒での処方が可能です。ただしその際は臭いなどの効果は薄れるために、効果が変わってしまうことが有ります。桃核承気湯など粉の方が効果が高いと感じられる薬もあります。 ただ飲めないよりは服用出来たほうが良いため、粉が苦手な方はご相談下さい。 粒のあつ漢方の例:葛根湯、葛根湯加川芎辛夷、半夏瀉心湯、半夏厚朴湯、五苓散料、小青竜湯、桂枝加芍薬湯、桃核承気湯、防風通聖散など
著者
資格
日本内科学会認定 認定内科医
日本消化器病学会認定 消化器病専門医
日本消化器内視鏡学会認定 内視鏡専門医
日本肝臓学会認定 肝臓専門医
日本消化管学会認定 胃腸科指導医
日本糖尿病学会
経歴
| 平成15年 | 東京慈恵会医科大学 卒業 |
|---|---|
| 平成15年 | 東京警察病院 |
| 平成23年 | JCHO東京新宿メディカルセンター |
| 平成29年 | 株式会社サイキンソーCMEO |
| 平成30年 | 東長崎駅前内科クリニック開院 |