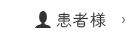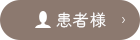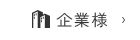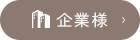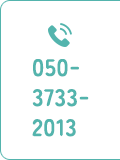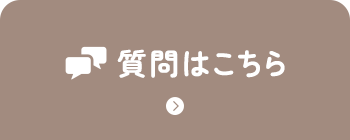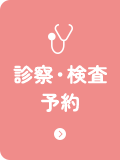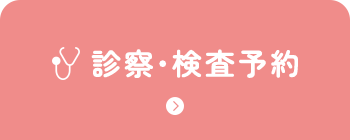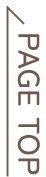目次
肝臓・胆のう・膵臓の検査・診察が予約不要
- 当日検査・当日結果説明が可能
- 同日の胃カメラ検査が可能
- 熟練の検査技師が検査※
※超音波学会所属の経験豊富な超音波検査専門技師が検査を担当します。診察は医師が担当します。

インターネット予約での検査も可能です。 希望される方はこちら
TEL:050-3733-2013
受付時間 / 平日9:00~12:00 土曜9:00~13:30
休診日 / 日曜・祝日
検査費用 :3割負担 約1,500円
採血検査やドップラー検査などが必要な場合の追加料金 1,000-2,000円程度
上記に初診料・再診料・薬剤費・処方箋料などが追加されます。
フィブロスキャン検査:3割負担で600円程度
保険適応の関係で採血や腹部超音波検査を合わせて行う場合があります。
※超音波学会所属の経験豊富な超音波検査専門技師が検査を担当します。
腹部超音波検査(腹部エコー検査)とは

空気、水、脂肪、血液などの組み合わせ次第で超音波の反射に影響が及ぶため、それぞれの差異を画像として映し出し、様々な疾患の診断に役立てています。
腹部エコー検査では、腎臓、膵臓、肝臓、胆のう、脾臓の状態を確認することが可能です。
当院では予約が無い方でも当日検査ができる場合もあります。午前検査を受けたい方は朝食を控えていただき、午後検査を受けたい方は昼食を控えていただければ、診察と診察の間の時間で対応できることもあります。土曜は他の患者様も多くいらっしゃいますので、平日の方がスムーズなご案内が見込めます。
検査結果は当日中の開示が可能です。
当院で検査を担当する臨床検査技師について
関東の複数の総合病院にて超音波検査を長年経験した実績があります。超音波検査については13年以上の経験がある熟練の臨床検査技師です。腹部、甲状腺、心臓、頸動脈、静脈といったあらゆる部位のエコー検査の対応が可能です。当院では、熟練の臨床検査技師と肝臓疾患のプロフェッショナルである医師で丁寧かつ正確な検査・診断を実現しております。
以下のような方は超音波検査をお勧めします
- 人間ドック、健診で肝障害や肝臓の数値の異常が判明した方
(TB(総ビリルビン)、AST(GOT)、ALT(GPT)、γGTP) - 健診で定期検査を勧められた方(胆のうポリープ、胆石、肝血管腫など)
- 腹痛(側腹部、みぞおちなどの痛み)がある方
- 糖尿病を患っている、もしくは、糖尿病が悪化してきている方
- B型・C型肝炎を患っている、もしくは過去に患っていた方
- 胆のうポリープや胆石がある方
- NAFLD/NASH(ナッシュ)、脂肪肝、肝硬変の疑いが強く、フィブロスキャン検査を受けた方が良い方
以下のような方は超音波検査(エコー検査)が
見えにくくなることがあります
1.プローベを当てづらい
過度に痩せている方などはお腹にプロ―べが上手く当たらず浮いてしまう恐れがあります。
2.骨や空気が間に入る
超音波が先に進んでいかなくなるため、肝臓の前に腸がある場合など検査に支障をきたす恐れがあります。また、頭蓋内や肺の中を検査することも難しくなります。食事中は胃の中に空気が貯まるため検査が難しくなります。
3.超音波が伝わりづらい
内臓脂肪や皮下脂肪が多い方は検査に支障が出ます。また、肝臓は身体の深部に位置しているため、全てを観察することは難しくなります。
4.息止めや複式呼吸が困難な方
腹式呼吸をすると内臓が下に下りてくるため超音波が伝わりやすくなります。一方で、粋止めや腹式呼吸が困難な方は検査に支障が出てしまいます。
当院の超音波検査の特徴
- 予約が無くても当日検査が可能な場合もある(食事制限が必要)
- WEB予約が可能
- エコー検査の結果は当日中に説明可能
- 午前、午後、土曜の検査にも対応
- 経験豊富な臨床検査技師と肝臓疾患のプロフェッショナルである医師の2名で
丁寧かつ正確な検査・診断を実現 - 肝臓以外の疾患も診断が可能なため、包括的な対応を実現
- 国内でまだ導入先が少ない最新鋭のフィブロスキャン検査機器を完備
超音波検査でのみ発見できる病気
肝臓:栄養の貯蔵、解毒など様々な作用を持つ臓器
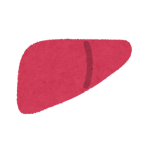
1、肝血管腫(かんけっかんしゅ)
肝臓の腫瘍の中で一番多く見つかる良性腫瘍で、血管の細胞でできています。大抵は良性ですが、場合によっては次第に肥大化していく恐れもありますので、注意深く経過を観察することが重要です。肥大化するタイプのものには悪性腫瘍(がん)もあるため、こまめに検査を受けることが望ましいでしょう。
少なくとも年に1回の腹部超音波検査をお勧めしております。
2、脂肪肝(しぼうかん)
肝臓に脂肪が蓄積された状態のことです。健診にて肝機能異常が判明し来院されるケースが増えております。高コレステロール血症や糖尿病などの生活習慣病と密接に関係しており、運動不足、飲酒習慣、メタボリックシンドロームなどによって引き起こされるとされています。従来は特に治療をすることはありませんでしたが、昨今では飲酒をしない方が肝硬変・肝臓がんを起こす場合(非アルコール性脂肪性疾患:NAFLD)が増加傾向にあるため、注意が必要です。検査では腹部エコーの他に血液検査も実施します。なお、当院では比較的導入している医療機関が少ないフィブロスキャン検査にも対応可能であり、肝硬変の進行度合いや肝臓の脂肪量を簡単に確認できるようになっています。
脂肪肝の診断を受けた方は、肝臓以外の臓器の疾患、血圧、コレステロールにご注意ください。
当院では脂肪肝診療と共に高血圧・高脂血症・糖尿病などの生活習慣病も併せて治療を行います。
3、肝嚢胞(かんのうほう)
水風船のように肝臓内部に水が蓄積した水風船のような状態です。腹部超音波検査で最もよく見かける良性の所見のひとつ、多くの場合は特段の症状は現れません。のう胞が肥大化するにつれて、腹部の圧迫感、膨満感などの症状を自覚するようになります。また、遺伝的な要因で腎臓にも同様ののう胞が複数生じることもあるため、ご注意ください。
4、慢性肝障害(まんせいかんしょうがい)・肝硬変(かんこうへん)
肝障害が長期間にわたって続いている状態を慢性肝炎といい、慢性肝炎が継続した結果、肝機能が不可逆的に低下してしまった状態が肝硬変です。慢性肝炎は発症原因としては、B型肝炎、C型肝炎、脂肪肝、自己免疫性肝疾患、飲酒習慣などが考えられます。原因特定および進行度合いの確認のため、しっかりとした検査が求められます。
当院では比較的導入している医療機関が少ないフィブロスキャン検査が可能であり、肝硬変の進行度合いを簡単に確認可能です。
また肝性肝炎、肝硬変は専門の治療も必要ですので肝臓内科の受診がのぞまれます。
5、肝腫瘍(かんしゅよう)
肝臓の中にできるできものの総称です。腫瘍には良性も悪性もあり、多種多様な種類があります。また、エコー検査で発見できる場合と発見が難しい場合があります。発見できない場合は、CT検査、MRI検査などの別の検査が必要となるため、提携先の医療機関をご紹介いたします。さらに、別の臓器で生じたがんが肝臓に転移しやすいという特徴があるため、大腸などの精密検査も必要となる場合もあります。
6、そのほか
肝内胆管拡張・肝内胆管結石・肝内石灰化・肝嚢胞性腫瘍・肝内気腫など
胆のう
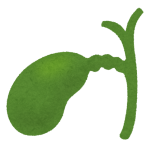
1、胆泥 (たんでい)
胆のうに蓄積した泥です。濃縮された胆汁や感染による炎症で生み出される場合もあります。がんなどの悪性腫瘍と似たような超音波像が映ることもあり、注意が必要です。また、泥で胆のう内部を正確に把握できないこともあるため、MRI検査などの精密検査を要する事もあります。
2、胆嚢結石(たんのうけっせき)
胆石のことです。胆のうの中に生じるものであり、胆管炎や胆のう炎を引き起こします。胆のうがんをあわせて発症するケースもあるため、詳しく検査することが求められます。特に、胆のう壁が肥厚しているケースや結石の後ろ側の胆のう壁を正確に検査できないこともあるため、要注意です。
たまたま検査で発見されたような症状のない胆石の場合は経過観察をすることがありますが、症状を有する胆石は胆のう摘出術をお勧めすることが有ります。
3、胆嚢腺筋腫症(たんのうせんきんしょう)
胆のう壁の全体もしくは一部が肥厚する良性の疾患です。健診や人間ドックを受診された方の約1%に見つかるとされています。悪性のものも存在するため、MRIなどで正確な区別を行った上で、経過を注視する必要があります。
完全に良性と判断できないケースは胆のう摘出術などの手術をお勧めるすることが有ります。
4、胆嚢ポリープ(たんのうぽりーぷ)
胆のうの中に生じる突起物で、健診や人間ドックの受診者のうち約10%で見つかる傾向にあります。大半は良性ですが、悪性のがんも存在するため注意が必要です。
基本的には定期的に腹部超音波検査を実施して経過を見ていきますが、1㎝を超えるものや形が不整なものはCT、MRI、超音波内視鏡などでの追加検査を行うこともあります。検査の結果良性と判断できないものに関しては胆のう摘出術をお勧めすることが有ります。
5、そのほか
胆嚢気腫・胆嚢腫瘍・胆嚢腫瘤・胆嚢腫大・びまん性胆嚢壁肥厚・胆管拡張・胆管気腫・胆管結石・胆管腫瘍・胆管壁肥厚など
膵臓
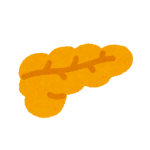
1、膵のう胞(すいのうほう)
膵臓の中に水がたまり水風船のようになります。膵液や炎症で生じる液体が溜まる場合(仮性膵のう胞など)、腫瘍から出る液体が溜まる場合(IPMNなど)など、タイプはまちまちです。腹部超音波検査のみでは良性・悪性を見極めることが困難なことが多く、CT・MRI、超音波内視鏡で精密検査を実施することもあります。
良性と判断された場合でも定期的な検査をお願いしています。
2、膵腫大(すいしゅだい)
その名の通り膵臓が膨張して肥大する病気です。膵炎などの炎症、腫瘍が原因となっていることもあり、状態を精査することが大切です。なお、膵臓は人によってサイズが異なるため、生まれつき膵臓のサイズが大きい方もいらっしゃいます。
腫大しているのみではなく、症状やそのほかの検査で異常がないかどうかも重要です。
3、膵萎縮(すいいしゅく)
腫大とは異なり膵臓が萎縮して薄くなる病気です。原因としては慢性膵炎が考えられます。萎縮によって膵臓の機能低下が起こる方もいらっしゃるため、精密検査の上で適切な治療を行うことが重要です。なお、生まれつき膵臓のサイズが小さい方もいらっしゃいます。
慢性膵炎で症状がある方の場合は継続的な内服加療が必要です。
4、膵腫瘍(すいしゅよう)
膵臓に生じる腫瘍は良性のこともあれば悪性のこともあります。悪性腫瘍の典型例である膵臓がんでは、発症初期に悪性かどうかを見極めることは難しく、膵腫瘍が発見されましたら、至急で精密検査を受けて状態を確認することが大切です。
5、そのほか
膵石・膵管拡張・膵腫瘤など
腎臓
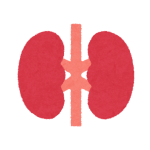
1、腎嚢胞(じんのうほう)
腎臓の中に水がたまり水風船のような病変が生じます。発症確率は相応に高く、単発あるいは多発する傾向にあります。良性の病変が大半ですが、サイズが大きくなると何かしらの症状が現れることがあります。また、遺伝的に多数ののう胞が生じることもあり、そのようなケースでは腎機能の低下につながる恐れもあります。
2、腎結石(じんけっせき)
腎臓内に生じた結石です。微小なものは自然と排出されることもありますが、サイズが大きなものは尿路に詰まり痛みを生じる恐れもあります(尿路結石)。内科や泌尿器科で適切な診療を受けることをお勧めします。
3、腎萎縮(じんいしゅく)
腎臓が標準サイズよりも小さな状態のことです。慢性腎機能障害によって腎臓が段々と萎縮していく恐れがあります。結石や糖尿病腎症が原因となり萎縮するケースもありますので、注意が必要です。
4、水腎症・腎盂拡張(じんうかくちょう)
何かしらの理由で尿が滞留し、腎臓内に蓄積してしまう病気です。腫瘍や結石によって引き起こされる恐れがあるため、状態をしっかりと検査することが重要です。重症の場合は水腎症という病気となります。
5、腎血管筋脂肪腫(じんけっかんきんしぼうしゅ)
腎臓でよく発見される良性の腫瘍です。脂肪、血管、筋から構成されています。経過を注視すれば問題ない場合がほとんどですが、稀に出血のリスクを伴うケースもありますので、注意が必要です。
6、腎腫瘍(じんしゅよう)
腎臓に生じる腫瘍は良性のものもあれば悪性のものもあります。
悪性腫瘍としては腎細胞がんがよく知られています。
7、そのほか
腎嚢胞性腫瘍・腎石灰化・馬蹄腎など
その他観察できる可能性のあるもの
胸水・心嚢水・腹部大動脈・腹水・脾腫・副脾
著者
資格
日本内科学会認定 認定内科医日本消化器病学会認定 消化器病専門医
日本消化器内視鏡学会認定 内視鏡専門医
日本肝臓学会認定 肝臓専門医
日本消化管学会認定 胃腸科指導医
日本糖尿病学会
経歴
| 平成15年 | 東京慈恵会医科大学 卒業 |
|---|---|
| 平成15年 | 東京警察病院 |
| 平成23年 | JCHO東京新宿メディカルセンター |
| 平成29年 | 株式会社サイキンソーCMEO |
| 平成30年 | 東長崎駅前内科クリニック開院 |