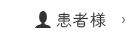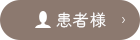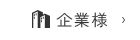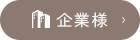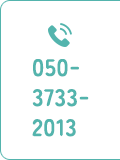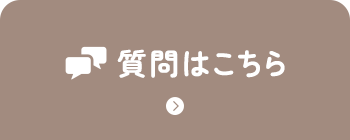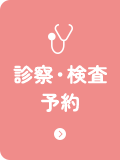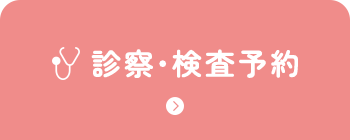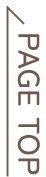目次
胃カメラとバリウムは、どちらも胃の疾患を見つけるために行う検査としてよく耳にしますが、どちらを選ぶのがよいのでしょうか?
胃カメラ検査で得られる情報はとても多いため確かにおすすめですが、バリウム検査が未だに行われていることにもきちんとした理由があります。
この記事では、胃カメラ検査とバリウム検査の両方のメリットやデメリットなど、それぞれの特性や検査上の注意点、受けられない人などを詳しく紹介します。
自身の検査をする際に最適な選択ができるよう、参考にしてください。
胃カメラとバリウムのそれぞれの特性を知ろう
胃カメラは直接胃の中を観察できるため、検査をするならリアルタイムでそのまま胃を診られる胃カメラのほうがよいと考える人も多いです。
しかし、胃カメラが受けやすく進歩した現在にもかかわらず、未だにバリウムのほうが受けやすいと感じる人もいます。
胃カメラとバリウムの、それぞれにある特性を知って、自身にとってどちらがより条件を満たす検査なのかをよく考え、選択しましょう。
胃カメラ(内視鏡検査)のメリット
胃カメラのメリットは胃のなかを直接見ることができるだけではありません。 ここでは、胃カメラ検査のメリットを紹介します。
早期の胃がんや小さい病変を発見しやすい
胃カメラは病変を直接観察できることがメリットです。
早期の胃がんは病変が小さいため、わずかな凸凹や色の違いで判断する必要があります。
バリウム検査で撮影される写真は白黒のみで表現されるもののため、色の違いはもちろんのこと、平坦な部分に起こった病変を見分けるのは困難です。
その点、胃カメラは病変が小さければ拡大鏡を使用し、模様や色も鮮明に分かるため、わずかな違いを見分けることに優れています。
胃がん以外にも食道がんもバリウムでは見つけにくく胃カメラで発見すされることがあります。
咽頭や喉頭などの喉の病気も胃カメラに軍配が上がります。
病変の一部採取が可能
胃カメラは検査でありながら、病変の一部採取が可能です。
胃カメラの先端には以下のように、便利な機能をもつ道具が備えられています。
胃カメラの先には道具を出し入れできる鉗子口(かんしこう)があるため、観察中に病変を発見した場合、病理検査のための生検(組織採取)が可能です。
肉眼的な診断以外にも細胞レベルの診断も同時に行えます。
そのためバリウムで異常があった方は胃カメラがお勧めされるわけです。
食道がんの発見率が高い
胃カメラは胃の観察のために食道を通りますが、その際に食道の病変も発見できます。
食道がんは早期の自覚症状がなく、発見の機会は健康診断のバリウムまたは内視鏡検査や、胃痛や胸やけなど食道がんとは別の症状で検査を行った際です。
食道がんは胃癌に比べて平たい病変があるため、バリウムでは見つけにくいです。
食道がんは治療も非常に厳しい疾患のため、早期発見が重要です。
バリウムも食道を通りますが、早期の食道がんを発見する能力は胃カメラのほうが高いといえます。
飲酒や喫煙歴の長い方は胃カメラでの検査をお勧めします。
鎮静剤を使用すれば眠った状態で検査可能
胃カメラ検査は鎮静剤や麻酔薬を使用することで、ぼんやりと眠った状態の間に検査が行えます。
バリウム検査では眠った状態での検査はできません。
胃カメラ(内視鏡検査)のデメリット
胃カメラ検査は病変を発見する性能が優秀ですが、デメリットもあります。 ここでは、胃カメラのデメリットを紹介します。
鎮静剤を使用しない場合は苦痛が伴う可能性がある
自治体で実施しているがん検診は費用が抑えられていますが、基本的には鎮静剤を使用しないため、鎮静剤を使用しない胃カメラ検査は苦痛が伴います。
健康診断を受ける医療施設によっては別途費用を追加することで、鎮静剤を用いた検査を行える場合もあります。
胃カメラ検査で鎮静剤を使って苦痛を少なく抑えられることは重要なポイントであるため、健康診断を申し込む際は事前に確認しましょう。
費用がやや高い
自覚症状が特にない胃カメラ検査や人間ドックなどは、自由診療で実費負担となる場合、費用は高めです。
施設にもよりますが実費の場合は10000円から15000円程度です。
胃カメラ検査では以下の場合に保険診療になります。
- 症状が有り、医師の診察によって胃カメラ検査が必要と認められた場合
- 健康診断で再検査指示があった場合の再検査
- 健康診断や自由診療で検査中に病変が見つかり、組織採取と病理検査を行った場合(全額保険ではない事もあり)
以上のように保険診療の場合は1~3割負担になります。
価格は3割負担で3000円から4000円程度になります。実際の検査では生検やピロリ菌検査などが発生する事もあるため、念のために少し多めに用意して臨むのが安心です。
喉の麻酔使用で数万人に一人がショック症状を起こす
胃カメラ検査は喉に対してスプレーやゼリーなどの表面麻酔を使用しますが、稀にアナフィラキシーショックを起こす場合があります。
表面麻酔は歯科治療で使用される麻酔と同じ種類と考えて差し支えのない、部分的な麻酔です。
アナフィラキシーショックを起こす確率は稀ですが、検査の計画の時点で鎮静剤や表面麻酔の使用を確認して、アレルギーがある、麻酔に不安があるなどの場合は検査前に医師に相談しましょう。
鎮静剤・麻酔薬が覚めるまでふらつく
鎮静剤・麻酔薬を使用した場合、終日にわたり自動車やバイクの運転ができません。
検査が終われば1~2時間ほど医療機関で休んでから帰宅しますが、それ以上の間、頭がぼんやりしたりふらついたりする状態が続く場合があります。
多くの医療機関で検査後の運転を禁止しているため、公共交通機関を利用するか家族による送迎が必要です。
使用される薬剤によっては翌日まで嘔気が残るケースが有ります。
バリウム検査(胃透視検査)のメリット
胃カメラ検査のメリット・デメリットを紹介しましたが、ここからはバリウム検査のメリットを紹介します。 胃がんの早期発見には胃カメラ検査のほうがおすすめとされるなか、バリウム検査にどのような必要性があるのかが、メリットから分かります。
費用が安い
バリウム検査は胃カメラ検査に比べると費用が安く済みます。
診療報酬点数から計算してもバリウム検査のほうが安いですが、もっと費用を抑えようと思った場合、自治体が行っている胃がん検診でバリウム検査が受けられれば、低額または無料で受けられる場合があります。
費用がネックで胃カメラを躊躇している人にも、胃がんの早期発見の機会がバリウム検査によって与えられています。
自治体の検診で広まっている検査ですので毎年受けることが出来る自治体が多いです。
胃全体が把握できる
バリウム検査は胃の表面にバリウムを薄く行き渡らせて撮影するため、一部しか映し出せない胃カメラと比べ、病変が胃のどの部分にあるのか、胃の形に異常がないかを知ることが可能です。
胃の表面に症状が出にくいスキルス性胃がんの場合、胃壁の厚みで病変を見極めるため内視鏡では分かりにくいですが、バリウムはこの疾患の発見が得意です。
胃全体や胃の動きの観察ができるため、手術前にバリウム検査が行われることもあります。
また食道アカラシアなど機能性の疾患の検索や形態的な変化を見るのに長けています。
バリウム検査(胃透視検査)のデメリット
バリウム検査も場合によっては必要な検査だということがメリットをみると分かりますが、やはりデメリットも知っておいたほうがいいでしょう。 ここでは、バリウム検査のデメリットを紹介します。
平たいがんや胃粘膜の色が分からない
バリウム検査は白黒の濃淡による画像で結果を判断するため、色や模様の違いや胃壁表面のわずかな異変の情報は得られません。 早期発見が重要な初期の胃がんは周囲との色の違いなどでしか確認できないことが多く、バリウム検査で発見することはむずかしいとされています。
被曝するリスク
バリウム検査はレントゲン撮影のため、多少なりとも被曝のリスクがあります。
もちろん人体に影響のない被曝量であり、放射線はがん治療にも使われるため、むやみに恐れる必要はありませんが、リスクを避けたい人にとってはデメリットといえるかもしれません。
げっぷをがまんする
バリウム検査では発泡剤を飲むためげっぷがでますが、だしてしまうと胃がしぼんで検査ができなくなります。
げっぷをしてしまうと再度発泡剤を飲まなければいけないため、がまんができない人には苦痛かもしれません。
胃液が多いと精度が下がる
バリウム検査は胃の表面にバリウムを付着させて病変の凸凹を見分けますが、胃液で薄まると検査の精度が下がってしまいます。 胃液は検査前に吸い取るようなことはできないため、胃液の多い人はバリウム検査に向いていません。 胃液が多いということは胃酸過多などの病気の可能性もあるため、胃痛や胸やけなどの症状がある場合は診察の際に相談しましょう。
排泄時のトラブル
バリウムは検査後に下剤を飲んで体内から残らず排出しなければいけません。 バリウムを排出せず溜めてしまうと硬くなって詰まってしまい、腸閉塞や腸穿孔などを引き起こす恐れがあります。
必ず下剤を服用する、水分を多めに摂るなどが必要です。
検査の受け方についての注意点
胃カメラ検査もバリウム検査も胃の病気を発見するための検査ですが、受け方には共通した以下のような注意点があります。
- 症状がない場合の検査はどちらも保険適用外
- 一定年齢以上は行政の胃がん検診の対象で、助成金や補助制度がある場合がある
- 検査で異常が見つかったら放置せずに受診をする
- 外来通院することを考えて、検査だけの内視鏡実施機関を選ばない。
- 費用面に関しては自治体の制度で安く抑えられる可能性はありますが、バリウム検査しかない・鎮静剤が選べないなど制限がある
『脂っこいもので胃もたれする』『あまり量が食べられなくなった』など、体質や年齢のせいだと思い込んでいたその症状が、じつは自覚症状だったということは少なくありません。
相談の結果、保険診療になる場合もあり、健診の結果も軽視するのは危険であるため、まずは受診することが大切です。
そして治療が必要となった場合の通いやすさを考えて検査する病院を選ぶのもおすすめです。
胃カメラ検査・バリウム検査を受けられない人
最後に、胃カメラ検査とバリウム検査を受けられない人をそれぞれ紹介します。
受けられないということは、自動的にもう一方を受けるしかないということになるため、どちらにするか迷ってしまい決められない人は参考になるでしょう。
胃カメラ検査を受ける際に注意が必要な人
以下のような人は胃カメラ検査を受けるさいに注意が必要です。
- 妊娠中:理屈上は検査可能ですが、メリットデメリットを考えて緊急性の無い場合は出産後に実施することがあります。
- 授乳中の人:全身麻酔や鎮静剤が使えません。局所麻酔のみで実施可能。
- 局所麻酔でアレルギー反応を起こしたことがある人:局所麻酔無しで全身麻酔での実施は可能。
- 抗血栓薬を服用中の人:内服内容によっては生検の実施を見送ります。
- 疾患のある人:疾患により使用できない薬剤や処置が有ります。
- 高血圧の人:コントロールされていない場合は出血のリスクが有ります。
- 指示に従えない人:検査中に体動が大きい場合は検査困難なケースが有ります。全身麻酔下でも動いてしまう人もいます。
- 高齢の人:全身麻酔の使用に一定のちゅいが必要です。
- パニック障害や嘔吐恐怖症、状態不良などの理由で胃カメラに耐えられない人
また、経鼻内視鏡ができない人については以下があります。
- 鼻の手術を行っている人の一部
- 鼻腔が骨格的に狭い人
- 人工肛門がある人(鼻腔や咽頭への刺激が人工肛門に負担をかける)
胃カメラ検査を受けられない場合を考えると、バリウム検査が未だに健康診断の選択肢にあるということが納得できます。 また、経鼻内視鏡も誰でも受けられるわけではないため、自分に合わせた選択が必要です。
バリウム検査を受けられない人
以下のような人はバリウム検査を受けられません。
- 妊娠中またはその可能性がある人
- 3日以上の便秘の人
- バリウム検査でひどい便秘になったことがある人
- 胃の手術歴がある人
- 透析中の人
- バリウムや発泡剤にアレルギーがある人
- 誤嚥しやすい人
- 検査機器の耐荷重(130kg)を超えている人
- 自分で立てない・体位を変換できない人
- 指示に従えない人
以上のような場合は、胃カメラ検査を受けられるか検討することになります。
まとめ
胃カメラ検査もバリウム検査も、それぞれメリット・デメリットがあるため、どちらがいいとは一概には決められないでしょう。 しかし、もしバリウム検査で要精密検査という結果が出た場合、結局胃カメラ検査を受けることになるため、何度も足を運ぶのが面倒な人は、最初から胃カメラ検査を選ぶといいかもしれません。
当院では、鎮静剤を使用した苦痛の少ない胃カメラ検査に対応し、経鼻胃カメラは6mmという細いカメラを使用しています。
ピロリ菌検査と結果報告を当日のうちに行えて、二酸化炭素を使用しているため検査後のお腹の張りも軽減できます。
『日本消化器内視鏡学会 消化器内視鏡専門医』を有する熟練の医師が行うの胃カメラ検査を安心してご検討ください。
著者
東長崎駅前内科クリニック 院長 吉良文孝
日本消化器病学会認定 消化器病専門医
日本消化器内視鏡学会認定 内視鏡専門医
日本肝臓学会認定 肝臓専門医
日本消化管学会認定 胃腸科指導医
日本糖尿病学会
日本肥満学会
平成15年 東京警察病院
平成23年 JCHO東京新宿メディカルセンター
平成29年 株式会社サイキンソーCMEO
平成30年 東長崎駅前内科クリニック開院