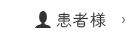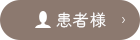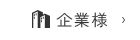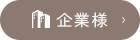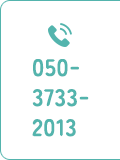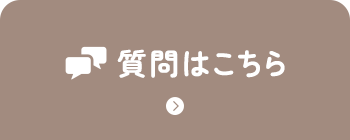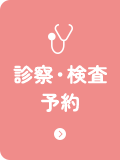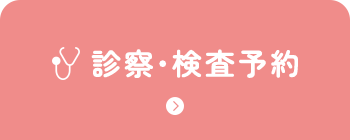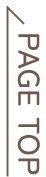目次
40歳を過ぎたら、早期発見で完治が可能といわれる大腸がんのために大腸カメラ検査をすすめられます。
その際に見つかることも多い大腸ポリープは、がん化する可能性がどのくらいあるのでしょうか?
この記事では、大腸ポリープの発生原因、がん化する確率、切除方法、予防方法といったさまざまな疑問について解説します。
「良性でした」といわれても、その正体が気になるポリープの正しい理解のために、ぜひ参考にしてください。
大腸ポリープとは
ポリープとは、粘膜などが盛り上がったり膨らんだりしてできる腫瘤(こぶ・しこり)の総称で、大腸ポリープはそれが大腸粘膜にできたものです。
ポリープには、きのこのような茎があるもの、茎のないもの、その中間の形や殆ど平たいものなど、さまざまな形状があります。
ここでは、大腸ポリープの種類や自覚症状について紹介します。
大腸ポリープの種類
ポリープは腫瘍性のポリープと、それ以外の非腫瘍性の2種類があります。
大腸ポリープの種類は以下の通りです。 非腫瘍性は基本的に良性で、放置してもがん化の可能性はほとんどありませんが、小さいポリープの場合、腫瘍性か非腫瘍性かの判別が困難なことがあります。
そして、大腸ポリープはほとんどが腫瘍性であるため、5mmを超えるポリープは基本的に切除するなどの早期治療が推奨されています。
大腸ポリープの自覚症状
大腸ポリープは小さいうちは全くといっていいほど自覚症状がありませんが、ポリープができた場所や大きくなった場合、細胞の質などによって、以下のような症状が現れる場合があります。
- 便に血が混ざる
- 便に粘液がつく
- 下痢になる
- 貧血になる
- ポリープが肛門から出てくる
硬い便が通過する部位にポリープがあると、擦れて出血を引き起こすことがあります。
健康診断などの便潜血検査でも発見できる異常であるため、心当たりがある場合や健診で指摘された場合は放置せず、医療機関を受診しましょう。
癌になる大腸ポリープとは
大腸癌(がん)は腺腫からが多い
大腸がんは腺腫からの発生が多いとされているため、切除することで大腸がんの罹患や大腸がんによる死亡の可能性が低下すると報告されています。
大腸ポリープの約8割といわれている腺腫には、数年かけてがんになる可能性があるものや、既にがんになっているものが含まれます。
一般的に、腺腫が時間をかけて徐々に大きくなって大腸がんに移行していくといわれているケースが、大腸がんの約9割です。
また最近では、正常な大腸粘膜からポリープではなく直接がんが発生する、浸潤や転移が早いタイプのも確認されているため、早期発見や定期的な検査がこれまで以上に重要視されています。
大腸ポリープが癌(がん)になる確率
良性の腫瘍性大腸ポリープである腺腫は、切除せず放置するとがんになる可能性があるとされています。
大腸ポリープの一部に癌が併存する割合である『担癌率(たんがんりつ)』の報告はいくつかありますが、腺腫の大きさ(直径)によって併存する癌の割合が上昇することが分かっています。
結果にばらつきがあるため一概にはいえませんが、直径5mm単位での担癌率を報告した以下の一例をみると、腺腫の大きさによる担癌率の数値が明らかになっています。
- ~5mm……0.4%
- 5~10mm……3.4%
- 10~15mm……12%
- 15~20mm……20.7%
- 20~25mm……26.6%%
- 25~30mm……32.1%
- 30mm~……28.7%
10mm以上になると急に担癌率があがるため、そうなる前に発見して切除することが大腸癌の効率的な予防となります。
ほかにも、大腸に大量のポリープが発生する遺伝性の病気『家族性大腸腺腫症』の場合、約50%の患者が15歳までに、95%の患者が35歳までにポリープが発生するといわれ、ほぼ100%が平均40歳前後までにがんを発症するといわれています。
家族性大腸腺腫症にかかった家族がいる場合や本人の罹患に対しての予防薬や治療薬はないとされるため、大腸ポリープの数にもよりますが、がん化する前に大腸を切除する処置が行われています。
しかし早期(10代)から内視鏡検査を開始し定期的に観察を行う、アスピリンの服用によりポリープの増大を抑制する治療法が研究されているなど、予防につなげることが重要であるため、該当する人は医師に相談しましょう。
また潰瘍性大腸炎の様な慢性的な炎症を来す疾患も大腸癌のリスクがあります。
そのた一定期罹患されている潰瘍性大腸炎の方は毎年の大腸カメラをお勧めしています。
大腸ポリープの発見・切除方法
大腸ポリープは検査方法がいくつかあり、ほとんどが大腸内視鏡検査中に切除が可能です。
ここでは大腸ポリープ発見のための検査方法と、内視鏡による切除方法を紹介します。
便潜血検査
便潜血検査は健康診断の際に行われる検査で、便のなかにヘモグロビンという血中タンパク質が含まれているかを調べます。
大腸ポリープがある場合、便が大きいポリープの場合は擦れて出血する場合があるためです。
しかし便潜血検査で陰性の場合もあるため、注意は必要です。
大腸カメラ(大腸内視鏡)
大腸カメラ検査は確実な診断が可能な、最も一般的な検査方法です。
カメラで直接観察し、病変を確認した場合はその場で組織採取ができます。
がん化していなければその場でポリープの切除ができ、日帰りも可能です。
一度は検査をお勧めします。
CTコロノグラフィ
手術後の癒着などがあり、大腸カメラ検査ができない場合に有効な検査です。
CTを利用した検査のため、患者様の身体の侵襲が少なく済みますが、大腸カメラのようにその場でのポリープ切除や組織採取はできません。
カプセル内視鏡
CTコロノグラフィ同様、大腸カメラが使用できない場合に用いられる検査方法で、小腸内も観察が可能です。
被曝や苦痛がないメリットがある一方で、組織生検やポリープ切除ができないというデメリットもあります。
また前処置の下剤が多いのも難点です。
下部消化管造影検査
ほとんど行われることはないですが、肛門からバリウムを注入しレントゲンで大腸を撮影するこの検査です。
ポリープのある正確な場所や大きさの他に、大腸の全体の状態も観察できます。
大腸カメラ同様、腸管内をきれいにするために下剤などを利用します。
内視鏡による大腸ポリープの切除方法
大腸ポリープの切除方法には以下のようにいくつかの方法があります。
大腸カメラでの切除が困難な場合のポリープや、がん化してリンパ節への転移がある場合は外科的な治療が行われます。
- ポリペクトミー
スネアと呼ばれるループ状のワイヤーを出してポリ―プにかけ、縛って切り取る方法で、直径5~10mm程度の茎のある形状のポリープに対して選択されます。 高周波電流を流して切り取る方法と、電流を流さずに切り取る方法(コールドポリペクトミー)があります。 - 内視鏡的粘膜切開術(EMR)
平坦な形状の、粘膜にあるポリープを切除する方法です。病変の下に生理食塩水を注射し、ポリープを持ち上げて膨らませます。 膨らませると、平坦なポリープでも筋層から離すことができるため、スネアで縛り高周波電流を流して切除します。 - 内視鏡的粘膜下層剥離術(ESD)
直径2cmを超える平坦で大きなポリープにも対応できる術式です。 切除するポリープの周囲にマーキングをして、EMR同様、生理食塩水を注射しポリープを持ち上げたら、さまざまなナイフを使いマーキングに沿って薄く病変を削ぎとります。
まとめ
大腸ポリープにはがん化の心配がないポリープも存在します。 しかし大腸ポリープについてはがんになる確率というよりも、まず早期発見のための検査が重要であるといえるでしょう。
日本人の死因で最も多いがんのなかでも上位を占める大腸がんは、早期発見によって完治が期待できる病気です。
大腸ポリープの発見も、便潜血陽性といわれた方も、当院にお任せください。
内視鏡専門医による苦痛の少ない大腸カメラ検査を安心してご来院下さい。