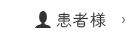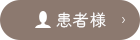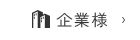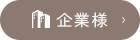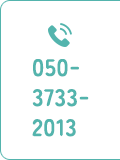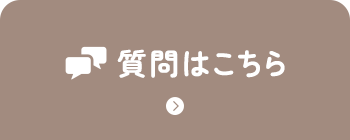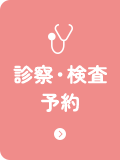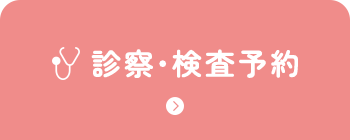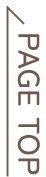人工知能(AI)を活用した大腸内視鏡検査 ― 最新研究から見えてきた可能性と課題
大腸内視鏡検査とAIの進化
大腸内視鏡検査は、大腸がんや前がん病変である腺腫性ポリープを早期に見つけるために欠かせない検査です。
近年は人工知能(AI)が導入され、医師の観察をリアルタイムに支援できるようになりました。
AIは内視鏡カメラ映像を解析し、病変の疑いがある部位を自動でマーキングするため、見逃し低減が期待できます。
Lancet誌に掲載された最新研究のポイント
2025年8月、医学誌「The Lancet Gastroenterology & Hepatology」に、ポーランドの多施設で行われた観察研究が掲載されました。
19名の内視鏡専門医による1,443件の大腸内視鏡検査を解析し、AI導入前後の腺腫検出率(ADR)の変化が報告されています。
- AI導入前(非AI使用・795件):ADR 28.4%
- AI導入後(非AI使用・648件):ADR 22.4%(約20%の相対低下、絶対6ポイント減)
- AI使用時(導入後):ADR 25.3%
すなわち、AIを使うと検出率は改善する一方で、AIを使わないと導入前より検出率が低下する傾向が示されました。AIの恩恵と同時に、運用上の注意点が浮き彫りになっています。
AIによる「スキル低下(デスキリング)」の懸念
研究では、AIに依存することで医師の観察・判断スキルが弱まる「デスキリング(deskilling)」が懸念点として指摘されました。
AIが利用できない状況や、AIのアラートが出にくい病変では、人の技量が検査品質を左右します。
- メリット:AIは見落としやすい微小病変の検出を後押しし、検査の均質化に寄与
- デメリット:過度な依存は医師の観察力・判断力の低下につながり、AI非使用時の検出率低下を招く恐れ
AIが苦手(検出しにくい)になり得るケース
AI内視鏡は、学習に用いる「鮮明で整った条件の画像」に強みがあります。以下のように観察条件が不良なケースでは、AIの支援効果が十分に発揮されない可能性があります。
- 前処置不良:便や残渣の残り、泡が多い、視界不良
- 腸管拡張が不十分:癒着・強い屈曲などで視野が取りづらい
- 不規則な動態:呼吸・蠕動・体位で読影が安定しない
このような症例では、医師の基本手技(洗浄・吸引・体位変換・送気/送水・適正な撤退時間の確保・観察範囲の工夫)がカギになります。AIを日常的に活用していても、“まず人間の観察を最適化する”姿勢が検出率維持に不可欠です。
まとめ
- AI内視鏡は検出率向上に有用だが、運用にはバランスが必要
- デスキリング回避のため、医師の観察・基本手技・教育を重視
- 条件不良症例では人の工夫が検査の成否を分ける
ご不明点はいつでもお問い合わせください。適切なタイミングでの大腸内視鏡検査が、将来の健康を守ります。