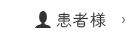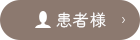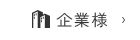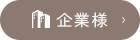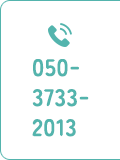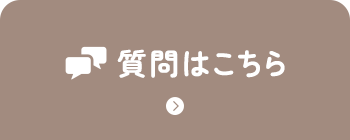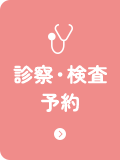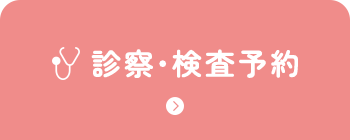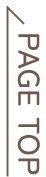見過ごせないサイン 急性虫垂炎の初期症状から典型的な痛みまで
急性虫垂炎のサインは、特徴的な痛みの変化や、腹痛以外の症状として現れることが多いです。
「いつものお腹の痛みと違うな?」と感じたら、これから説明するサインに当てはまらないか注意深く観察してみましょう。
みぞおちやへそ周りの不快感
急性虫垂炎の最初のサインとして、胃がある「みぞおち」の辺りや、おへその周りに、重苦しい不快感や鈍い痛みを感じることがあります。
これは、虫垂の炎症が始まったばかりの段階で見られる症状です。
多くの場合、この段階では「胃の調子が悪いのかな」「何か悪いものを食べたかな」と考えてしまいがちです。
しかし、この後に続く症状の変化に気づくことが、早期発見につながります。
この初期の不快感が、急性虫垂炎を見分ける最初のきっかけとなるかもしれません。
痛みが右下腹部へ移動する特徴的な経過
急性虫垂炎の非常に特徴的な症状の一つが、痛みの場所が変わることです。
最初に感じたみぞおちやおへそ周りの痛みが、数時間から半日ほどかけて、徐々に右下腹部(おへそと右側の腰骨を結んだ線の、やや下あたり)へと移動していきます。
この痛みの移動は、炎症が虫垂のある場所に限局していく過程で起こると考えられています。
最初は漠然としていた痛みが、右下腹部に集中し、鋭い痛みに変わってくることが多いでしょう。
「痛む場所が変わってきたな」と感じたら、急性虫垂炎の可能性を強く疑うべきサインです。
発熱、吐き気、嘔吐、食欲不振などの併発症状
腹痛と合わせて、次のような症状が現れることも急性虫垂炎のサインです。
| 症状 | 特徴 |
|---|---|
| 発熱 | 37℃台から38℃台の微熱から中程度の熱 |
| 吐き気 | ムカムカする感じ |
| 嘔吐 | 実際に吐いてしまうこと |
| 食欲不振 | まったく食欲がなくなる、食べ物を見たくない |
これらの症状は、体内で炎症が起きていることを示しています。
特に、右下腹部の痛みに加えて、これらの症状が複数見られる場合は注意が必要です。
腹痛だけでなく、全身の状態にも目を向けることが大切になります。
歩行や咳、振動で響く腹痛の感覚
炎症が虫垂の壁を越えて、お腹の内側を覆っている膜(腹膜)にまで広がると、腹膜刺激症状と呼ばれるサインが現れます。
具体的には、歩いたり、咳をしたり、体を揺らしたり、階段を下りたりすると、その振動が右下腹部に響くように痛む感覚です。
お腹を押さえた時よりも、押さえた手を急に離した時に強い痛みを感じる(反跳痛)のも、腹膜刺激症状の一つです。
これは、炎症がかなり進行している可能性を示す重要なサインと考えられます。
体を動かすと痛みが響くようになったら、早急に医療機関を受診することを検討しましょう。
子供や高齢者における非典型的な症状への注意
子供の場合、自分の症状をうまく言葉で表現できないことがあります。
なんとなく元気がない、食欲がない、機嫌が悪い、お腹を触られるのを嫌がる、といった変化がサインとなるかもしれません。
嘔吐や下痢だけが目立つこともあります。
一方、高齢者の場合は、加齢によって痛みの感覚が鈍くなっていたり、他の病気の症状と区別がつきにくかったりすることがあります。
発熱などの典型的な反応がはっきり現れないことも少なくありません。
そのため、診断が遅れて重症化しやすい傾向にあります。
子供や高齢者の場合は、普段と違う様子が見られたら、たとえ典型的な症状が揃っていなくても、急性虫垂炎の可能性を考えて早めに医師に相談することが大切です。
いつもの腹痛との違いを見分けるポイント
普段経験する腹痛と、急性虫垂炎が疑われる腹痛には、いくつか見分けるポイントがあります。
| チェックポイント | 急性虫垂炎の疑いがある場合 | いつもの腹痛(例: 胃腸炎、便秘など) |
|---|---|---|
| 痛みの始まり方と場所 | 最初はみぞおちやおへそ周り、次第に右下腹部へ移動 | 最初からお腹全体や下腹部など、痛む場所が移動しないことが多い |
| 痛みの強さの変化 | 時間とともにどんどん痛みが強くなる | 痛みに波があったり、排便などで和らいだりすることがある |
| 痛みの性質 | 持続的で鋭い痛み、体を動かすと響く | キューっとする痛みや鈍い痛みが多い |
| 腹痛以外の症状 | 発熱、吐き気、嘔吐、食欲不振などを伴うことが多い | 下痢を伴うことが多い(胃腸炎)、発熱はないことが多い |
| 市販薬(痛み止め)の効果 | ほとんど効かない、または一時的にしか効かない | 効くことがある |
もちろん、これらの違いはあくまで目安であり、自己判断は禁物です。
「いつもと違う」「何かおかしい」と感じる強い腹痛がある場合は、決して我慢せず、できるだけ早く医療機関を受診するようにしましょう。
急性虫垂炎の診断 病院での検査プロセスと特定方法
急性虫垂炎の疑いがある場合、病院での診断が非常に重要になります。
医師は、患者さんの症状を詳しく聞き、身体を診察し、必要な検査を行うことで、正確な診断を目指します。
ここでは、急性虫垂炎を特定するための具体的な検査プロセスについて解説します。
受診すべき診療科 外科または消化器科の選択
急性虫垂炎が疑われる症状がある場合、一般的には外科、または消化器内科・胃腸科を受診することが推奨されます。
夜間や休日などで緊急性が高い場合は、救急外来を受診してください。
医療スタッフによる問診 詳細な症状の聞き取り
診察の第一歩は、医療スタッフによる問診です。
いつから症状が始まったか、腹痛の場所はどこか、痛みはどのように変化してきたか(例えば、みぞおちから右下腹部痛へ移動したか)、発熱、吐き気、嘔吐、食欲不振などの他の症状はあるか、などを詳しく質問されます。
正確な情報を伝えることが、迅速な診断につながります。
お腹の触診 圧痛や筋性防御の確認
問診に続いて、医師はお腹を直接触って診察します(触診)。
右下腹部を中心に、押したときに痛みを感じる場所(圧痛点)や、お腹の筋肉が硬くなっている状態(筋性防御)、押して離したときに痛みが響くか(反跳痛)などを確認します。
これらの所見は、急性虫垂炎による腹膜への刺激や炎症の広がり具合を知るための重要な手がかりとなります。
問診と医師による診察で大体虫垂炎かどうかの判断は目星がつきます
炎症の有無を確認する血液検査(白血球数・CRP)
採血検査では虫垂炎特有の検査項目はありません。体の中で炎症が起きているかどうか、炎症の程度がどの程度かを調べるために、血液検査を行います。
急性虫垂炎では、細菌感染や炎症に反応して白血球の数が増加したり、CRP(C反応性タンパク)という炎症を示す数値が上昇したりすることが一般的です。
具体的には、白血球数が10,000/μL以上、CRPが0.3mg/dL以上などの数値が炎症の目安となりますが、これらの数値だけで診断が確定するわけではありません。
採血の結果がないと診断できない事はなく、専門医であれば採血なしでのおおよその診断は可能です。
診断の決め手となる画像検査 CT検査とエコー検査(超音波検査)
診断を確定し、炎症の程度や合併症の有無を評価するために、画像検査が非常に重要です。
| 検査方法 | 特徴 | 主な対象 |
|---|---|---|
| CT検査 | X線を使って体の断面を撮影。虫垂の腫れや周囲の状況を詳細に観察可能。 | 大人、高齢者 |
| エコー検査(超音波検査) | 超音波を使って体内の様子を観察。放射線被ばくがなく、手軽に行える。 海保学的な理由で超音波検査では診断できない事も少なくない。 | 子供、妊婦 |
CT検査は、腫れた虫垂や、虫垂の壁の肥厚、糞石(便の固まり)、周囲への炎症の広がり、膿のたまり(膿瘍)などを高い精度で確認できます。
しかしCT検査は緊急で実施が出来る施設が限られています。
一方、エコー検査(超音波検査)は、放射線の心配がないため、子供や妊娠中の女性に第一選択として用いられることが多い検査です。しかし、超音波検査では体格や腸内ガスの影響で観察しにくい場合もあり、観察できる範囲に限界があるので、CTに比べて診断能が落ちることが多いです。
これらの画像検査の結果は、急性虫垂炎の診断において決定的な役割を果たします。
他の病気(胃腸炎、婦人科疾患など)との見極め
右下腹部痛を引き起こす病気は、急性虫垂炎以外にもたくさんあります。
例えば、感染性胃腸炎、大腸憩室炎、尿路結石、女性の場合は卵巣嚢腫の茎捻転や骨盤内炎症性疾患(PID)などが挙げられます。
問診、触診、血液検査、画像検査の結果を総合的に評価し、これらの他の病気ではないことを確認することも、正確な診断には不可欠です。
症状が似ていても原因が全く異なる場合があるため、慎重な見極めが求められます。
急性虫垂炎の治療法 保存的治療と手術(腹腔鏡・開腹)の選択
急性虫垂炎と診断された場合、治療法は主に2つに分けられます。
炎症の程度や患者さんの状態に応じて、抗生物質で炎症を抑える保存的治療か、炎症を起こしている虫垂を切除する手術が選択されます。
それぞれの方法には特徴があり、医師が総合的に判断します。
抗生物質(抗生剤)による保存的治療とその適用条件
保存的治療とは、手術をせずに抗生物質(抗生剤)の投与によって炎症を抑える方法を指します。
点滴や飲み薬で治療を進めます。
この治療法は、急性虫垂炎の中でも炎症が比較的軽度で、虫垂の破裂(穿孔)や膿が溜まっている状態(膿瘍形成)がない場合に選択されることが多いです。
具体的には、腹膜炎の兆候が見られない、かつ全身状態が安定している場合などが適用条件となります。
入院が必要ではないケースもあります。
抗生物質によって炎症が治まれば、手術を回避できる可能性があります。
ただし、効果が見られない場合や、症状が悪化した場合は、速やかに手術へ移行する必要があります。
保存的治療のメリットと再発の可能性
保存的治療の最大のメリットは、手術による体への負担や傷跡を避けられる点です。
麻酔のリスクや手術に伴う合併症の心配がありません。
しかし、デメリットとして再発の可能性があります。
研究報告によって差はありますが、保存的治療後に約10%~30%程度の確率で急性虫垂炎が再発するといわれています。
一度炎症が治まっても、虫垂自体は残っているため、再び炎症を起こすリスクが残るのです。
治療期間が手術よりも長くなる場合もあります。
再発のリスクを考慮し、医師とよく相談したうえで治療方針を決めることが重要です。
手術(虫垂切除術)が必要となる判断基準
手術(虫垂切除術)は、急性虫垂炎の根本的な治療法です。
特に以下のような場合は、手術が必要と判断されることが多いです。
まず、炎症が強く、虫垂が破裂する危険性(穿孔リスク)が高い場合です。
画像検査で虫垂の腫れが著しい、虫垂の壁が薄くなっている、糞石(便の固まり)が大きいといった所見があれば、早期の手術が推奨されます。
また、すでに虫垂が穿孔して膿がお腹の中に広がっている状態(腹膜炎)や、虫垂の周りに膿が溜まっている状態(膿瘍形成)が確認された場合も、緊急手術の対象となります。
保存的治療を開始したものの、抗生物質の効果が見られず症状が悪化する場合や、一度治まったものの短期間で再発した場合も、手術が検討されます。
これらの判断は、症状、診察所見、血液検査の結果、CTなどの画像検査の結果を総合的に評価して行われます。
迅速な判断が、重篤な合併症を防ぐために不可欠です。
体への負担が少ない腹腔鏡手術の特徴と流れ
現在、急性虫垂炎の手術では腹腔鏡手術が主流となっています。
お腹に3~4カ所、5mm~1cm程度の小さな穴を開け、そこから腹腔鏡(カメラ)と専用の細い手術器具を挿入して行う手術です。
腹腔鏡手術の大きな特徴は、患者さんの体への負担が少ないことです。
傷が小さいため術後の痛みが比較的軽く、回復が早い傾向にあります。
美容的な観点からも優れており、入院期間も短縮できることが多いです。
通常、手術時間は炎症の程度にもよりますが、1時間~2時間程度です。
手術の流れとしては、全身麻酔の後、おへそのあたりなどから二酸化炭素ガスでお腹を膨らませ、視野を確保します。
次にカメラと器具を挿入し、モニターで内部を確認しながら、虫垂を根元から切除します。
切除した虫垂は小さな穴から体外へ取り出します。
感染のリスクも開腹手術に比べて低いとされていますが、高度な技術が必要となるため、執刀医の経験も重要です。
開腹手術が選択される具体的なケース
腹腔鏡手術が広く行われるようになっていますが、開腹手術が選択される、あるいは腹腔鏡手術から途中で開腹手術に移行する場合もあります。
具体的なケースとしては、まず、虫垂の炎症が非常に強く、周囲の臓器との癒着(組織がくっついてしまうこと)が激しい場合が挙げられます。
このような状況では、腹腔鏡手術では安全に虫垂を剥がしたり切除したりするのが困難なことがあります。
また、虫垂がすでに破裂し、広範囲に膿が広がっている重度の腹膜炎の場合も、お腹の中全体を直接見て、きれいに洗浄するために開腹手術が必要となることが多いです。
過去に何度も腹部の手術を受けていて癒着が予想される場合や、腹腔鏡手術の操作中に予期せぬ出血が起きた場合なども、安全を最優先して開腹手術に切り替えられることがあります。
開腹手術は、右下腹部を数cm~10cm程度切開して行います。
腹腔鏡手術に比べて傷は大きくなりますが、直接患部を見て確実に処置できるという利点があります。
入院期間の目安 手術方法や経過による違い
急性虫垂炎の治療における入院期間は、選択された治療法や手術後の経過によって異なります。
あくまで目安ですが、一般的な期間は以下の通りです。
| 治療法・手術方法 | 入院期間の目安 | 備考 |
|---|---|---|
| 保存的治療 | 5日~10日程度 | 抗生物質の効果や炎症の治まり具合による |
| 腹腔鏡手術 | 3日~7日程度 | 術後の経過が順調な場合 |
| 開腹手術 | 7日~14日程度 | 腹腔鏡手術より回復に時間がかかる傾向 |
| 穿孔・腹膜炎 | 2週間以上かかることも | 炎症の程度や合併症の有無により大幅に変動 |
保存的治療の場合、抗生物質の点滴が不要になり、炎症反応が落ち着き、食事が摂れるようになれば退院可能です。
手術の場合、腹腔鏡手術は傷が小さく回復が早いため、比較的短期間で退院できることが多いです。
一方、開腹手術や、穿孔して腹膜炎を起こしていた場合は、お腹の中の洗浄やドレーン(排液管)の留置などが必要になることがあり、入院期間が長くなる傾向があります。
いずれの場合も、術後の痛みの管理、食事の開始時期、合併症の有無などによって期間は変動します。
放置するリスク 穿孔や腹膜炎といった重篤な合併症
急性虫垂炎を疑う症状があるにもかかわらず、治療せずに放置することは非常に危険です。
「ただの腹痛だろう」と軽く考えて我慢していると、命に関わるような重篤な合併症を引き起こす可能性があります。
最も注意すべき合併症は、虫垂が破れてしまう穿孔です。
炎症が進んで虫垂の壁がもろくなると、内部の圧力に耐えきれずに穴が開いてしまいます。
虫垂内部には細菌を含んだ内容物があるため、それがお腹の中に漏れ出すと、腹膜(お腹の内臓を覆う膜)に広範囲な炎症が起こります。
これが腹膜炎です。
腹膜炎になると、激しい腹痛、高熱、頻脈、嘔吐などの症状が現れ、お腹全体が硬くなります。
治療が遅れると、細菌が血液中に入り込んで全身に広がる敗血症という危険な状態に陥ることもあります。
また、虫垂の周りに膿がたまる膿瘍(のうよう)を形成することもあります。
これらの合併症は治療を複雑にし、入院期間の長期化や後遺症のリスクを高めます。
急性虫垂炎の疑いがあれば、速やかに病院を受診することが何よりも重要です。
退院後の注意点 食事制限、運動、仕事復帰のタイミング
無事に退院した後も、しばらくは無理をせず、体に負担をかけない生活を心がけることが大切です。
特に術後の食事、運動、仕事復帰については、医師の指示に従いましょう。
食事については、入院中から徐々に流動食、おかゆ、普通食へと段階的に戻していきますが、退院後もしばらくは消化の良い、柔らかいものを中心に摂るのがおすすめです。
暴飲暴食、脂っこいもの、刺激の強い香辛料、アルコール、炭酸飲料などは、腸に負担をかけるため、少なくとも術後1ヶ月程度は控えるのが望ましいです。
食物繊維は便通を整えるのに役立ちますが、摂りすぎるとガスが溜まりやすくなるため、様子を見ながら少しずつ増やしましょう。
運動に関しては、軽い散歩程度であれば退院後すぐに開始できますが、腹筋を使うような激しい運動や重い物を持つ作業は、傷の回復を妨げたり、痛みを引き起こしたりする可能性があるため、術後1ヶ月程度は避けるように指示されることが多いです。
腹腔鏡手術か開腹手術かによっても制限の度合いは異なります。
仕事復帰のタイミングは、職種や回復の程度によって個人差があります。
デスクワーク中心であれば、術後1~2週間程度で復帰可能な場合が多いですが、力仕事や体を激しく動かす仕事の場合は、1ヶ月以上の休養が必要になることもあります。
いずれも自己判断せず、退院後の診察時に医師に相談し、許可を得てから再開するようにしてください。
焦らず、ゆっくりと元の生活リズムに戻していくことが大切です。