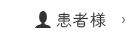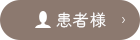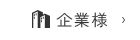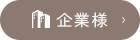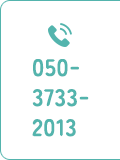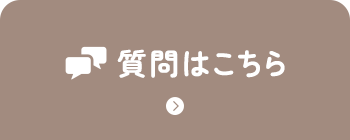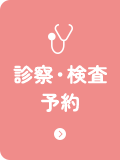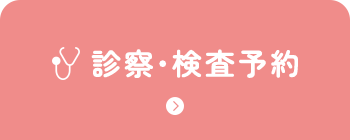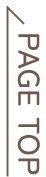目次
好酸球性食道炎:症状、原因、治療法について
好酸球性食道炎(Eosinophilic Esophagitis, EoE)は、アレルギー性の慢性炎症性疾患の一種で、食道粘膜に好酸球と呼ばれる白血球の一種が異常に増加することで引き起こされます。
この疾患は、嚥下困難(飲み込みにくさ)や胸やけなどの症状を引き起こし、生活の質に大きな影響を及ぼします。
本記事では、好酸球性食道炎について、症状、原因、診断、治療法の順に詳しく解説します。
好酸球性食道炎の症状とは?
好酸球性食道炎の主な症状は、年齢や個人によって異なるものの、以下のような特徴があります。
- 嚥下困難(Dysphagia): 食べ物を飲み込む際に違和感を覚えたり、固形物が飲み込みにくいと感じることがあります。特に成人ではこの症状が顕著です。
- 食物閉塞(Food Impaction): 食べ物が食道に詰まることで緊急医療が必要になる場合があります。
- 胸やけや胸の痛み: 胃酸の逆流とは異なる胸部不快感が生じることがあります。
- 慢性的な喉の痛みや咳: 慢性的な咳がみられることもあります。
これらの症状が長期的に続く場合や治療に反応しない場合、専門的な診断が必要です。
一般的な逆流性食道炎と症状がほとんど同じため見逃されていることが多い疾患でもあります。
好酸球性食道炎の原因とは?
難病に指定されているため、好酸球性食道炎の原因は完全には解明されていませんが、以下の要因が関与していると考えられています。
アレルギー反応:
食物アレルギーが最も一般的な原因とされており、乳製品、小麦、卵、大豆、ナッツ類などが関与している可能性があります。また、吸入性アレルゲン(例:花粉やダニ)も悪化因子となることがあります。免疫系の異常:
好酸球は通常、体内の寄生虫や感染に対する防御に関与していますが、過剰に反応することで食道の炎症を引き起こすと考えられます。遺伝的要因:
家族にアレルギー疾患(喘息、アトピー性皮膚炎など)の既往がある場合、発症リスクが高いとされています。
好酸球性食道炎の患者の多くは、アレルギー性鼻炎や喘息など他のアレルギー疾患を併発しています。
この点を考慮すると、アレルギー全般の包括的な管理が重要です。
好酸球性食道炎の診断方法
好酸球性食道炎を診断するためには、内視鏡検査と病理組織検査が必要です。
内視鏡検査:
食道粘膜にリング状の狭窄や白色プラーク(粘液の蓄積)が見られることがあります。
内視鏡検査は、食道の異常な状態を直接観察するために必要です。生検(Biopsy):
食道から複数個所採取した組織を顕微鏡で確認することで、好酸球が15個/高倍率視野以上検出される場合、診断が確定します。アレルギー検査:
血液検査や皮膚プリックテストを行い、食物や環境アレルゲンに対する反応を調べます。- CT検査:
胸部CT検査にて食道の全体的な浮腫が見られることがあります
これらの検査結果を総合的に評価することで、他の疾患(例:胃食道逆流症など)との鑑別が行われます。
採血検査で好酸球が多い必要はなく、採血上の異常は認められない事がほとんどです。
好酸球性食道炎の治療法
好酸球性食道炎の治療は、主に症状の管理と再発の予防を目的としています。以下は、一般的な治療法です。
1. 食事療法:
食物アレルギーが原因である場合、特定の食材を除去することで症状が改善することがあります。
- 6大アレルゲン除去食(Six Food Elimination Diet, SFED):
乳製品、小麦、卵、大豆、ナッツ、魚介類を一時的に除去し、徐々に食材を再導入する方法です。
この治療法で軽減する事もありますが、食事制限が難しいことと効果が不明瞭なこともあり、浸透していない治療法です。
2. 薬物療法:
- 一部のステロイド薬の経口投与:
主に局所ステロイド(例:フルチカゾン、ブデソニド)が使用され、食道の炎症を抑える効果があります。これらは吸入ステロイドとして処方されることが多く、経口摂取する形で用いられます。
日本では保険適応となる薬剤がないため、保険診療内でのステロイド治療は不可能です。 - プロトンポンプ阻害薬(PPI):
胃酸分泌を抑えることで、症状が改善する患者もいます。
3. 内視鏡的治療:
重度の食道狭窄がある場合、内視鏡的に食道を拡張する治療が行われることがあります。この処置は症状緩和に有効ですが、根本治療ではないため、他の治療法と併用する必要があります。
まとめ
好酸球性食道炎は、適切な診断と治療を受けることで、症状の改善と生活の質の向上が期待できます。
特に、早期発見と治療が重要であり、食事療法や薬物療法を通じて症状を効果的に管理することが可能です。
嚥下困難や胸やけなどの症状が続く場合は、専門医を受診し、適切な治療を受けることをお勧めします。
痛くない辛くない胃カメラ、鼻と口から選択当日の予約なし検査も実施
引用文献
- Liacouras, C. A., Furuta, G. T., Hirano, I., Atkins, D., Attwood, S. E., Bonis, P. A., ... & Dellon, E. S. (2011). Eosinophilic esophagitis: updated consensus recommendations for children and adults. Journal of Allergy and Clinical Immunology, 128(1), 3-20.e6.
- Dellon, E. S., & Liacouras, C. A. (2014). Advances in clinical management of eosinophilic esophagitis. Gastroenterology, 147(6), 1238-1254.
著者
東長崎駅前内科クリニック 院長 吉良文孝
日本消化器病学会認定 消化器病専門医
日本消化器内視鏡学会認定 内視鏡専門医
日本肝臓学会認定 肝臓専門医
日本消化管学会認定 胃腸科指導医
日本糖尿病学会
日本肥満学会
平成15年 東京警察病院
平成23年 JCHO東京新宿メディカルセンター
平成29年 株式会社サイキンソーCMEO
平成30年 東長崎駅前内科クリニック開院