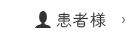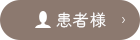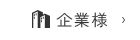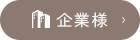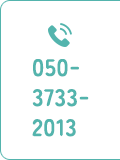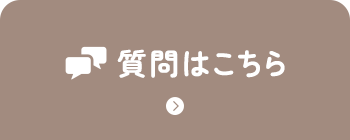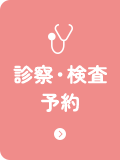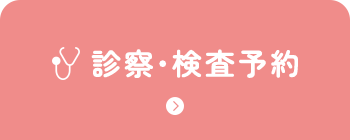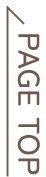こんにちは。今回は「肝硬変(かんこうへん)」という病気について、わかりやすく解説していきます。
「肝硬変」と聞くと、重い病気のイメージを持つ方も多いかと思います。実際、早期発見・早期治療がとても大切な病気ですが、しっかりと知識を持つことで、進行を防ぐことも可能です。
肝硬変とは
肝硬変とは、肝臓の細胞が壊れ、線維(せんい)という硬い組織に置き換わってしまう病気です。肝臓が「かたくなる」ことで、機能が低下し、さまざまな身体の不調を引き起こします。
肝硬変の主な原因
肝硬変になる原因はいくつかありますが、代表的なものは以下のとおりです。
B型・C型肝炎ウイルスの感染
→ 長期にわたってウイルスが肝臓に炎症を起こし、進行していくケースです。
アルコールの過剰摂取
→ 長年の飲酒習慣が肝臓に負担をかけ、徐々に肝硬変へ進行します。
非アルコール性脂肪性肝疾患(NAFLD/NASH)
→ 食生活の乱れや生活習慣病が関係する、近年増加傾向の病因です。
自己免疫性肝炎・遺伝性疾患
→ 稀ですが、体の免疫異常や遺伝によるものもあります。
肝硬変の症状
初期には自覚症状が少なく、気づかないこともあります。進行すると次のような症状が現れます。
・全身のだるさ・食欲不振・体重減少
・黄疸(皮膚や目が黄色くなる)
・腹水(お腹に水がたまる)
・吐血・下血(消化管出血)
・意識障害(肝性脳症)
・皮膚に赤い斑点(クモ状血管腫)や手のひらの赤み(手掌紅斑)
治療と予防・検査
肝硬変は完全に元に戻すことが難しい病気ですが、原因に応じた治療で進行を抑えることができます。
また、肝硬変は初期症状が少なく、検査で初めて見つかることが多い病気です。大切なのは肝硬変に移行する前に、検査による早期発見と治療をすることです。
●当院で行う主な検査の種類
血液検査…肝硬変のスクリーニング(初期発見)や進行度の評価に役立ちます。
腹部超音波検査…肝臓の形状変化(表面の凹凸、サイズの縮小など)や腹水の有無を確認
フィブロスキャン検査…肝臓に振動を与えて硬さ(線維化の程度)を測定
胃カメラ検査…肝硬変が進むと「食道静脈瘤(しょくどうじょうみゃくりゅう)」ができやすくなるため、胃カメラで静脈瘤の有無や破裂リスクを確認
●治療
肝炎ウイルスに対する抗ウイルス薬
禁酒・栄養指導・運動療法
肝性脳症や腹水への対症療法
肝移植(重度の場合)
日常生活で気を付けたいこと
肝硬変の進行を防ぐには、生活習慣の見直しがとても大切です。
・塩分を控えたバランスの良い食事
・適度な運動(無理のない範囲で)
・定期的な血液検査・フィブロスキャン検査や超音波検査などの画像検査
・飲酒は控える(できれば禁酒)
肝硬変は「沈黙の臓器」と呼ばれる肝臓の病気のひとつで、気づかないうちに進行してしまうことがあります。ですが、早期発見と適切な治療・生活習慣の改善によって、日常生活を問題なく送れる方もたくさんいます。
「少し疲れやすい」「健診で肝臓の数値が悪かった」などのサインがある場合は、ぜひ早めに当院でご相談くださいね。
診察のご予約はホームページまたはLINEからどうぞ!